関連記事

保護中: 不思議なちゃんぽん
そういえば、仕事で富山県に行った時のこと。 むこうは「うどん」が美味しい事で有名 ...
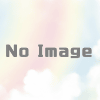
保護中: 今年の桃
今年の桃は当たり年だと思う。非常に安くて美味しいものが溢れている。毎年桃はケース ...
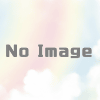
保護中: クリエイティブな人
先日本屋に行った。とあるビジネス書が欲しくて探しに来た。ついでに色々な本を見て ...
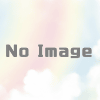
保護中: 電車の中でケームする奴ら
これね、 止めろ。 理屈じゃなく、 迷惑だ。 バカが勢い余って、 オレに肘を入れ ...

保護中: 天下一
天下一、などと言われて素通りできようか、いや、できまい。 というわけでコンビニで ...












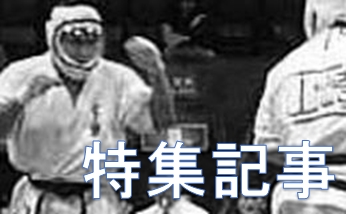









ディスカッション
コメント一覧
松原隆一郎
落語、私はよく分からないが、じっくり聴く人は多いみたいですね。身振りはあまり関係ないのかしら。
私が最近聴いて(見て)凄いと思ったのは、やはり談志。「鼠穴」で、火事で逃げまどうシーンで、ほんとうに談志の周りに熱風が吹いているように見えた。爆笑問題の太田さんにそう言ったら、「自分もそう見えた」と仰ってました。
あと、喬太郎。このヒトも天才ではないか、と感じます。躁鬱っぽいし。
植竹孝幸
松原先生
落語が再現芸術でありながら演劇や舞踏と一線を画して考えられるのは、演劇・舞踏といった芸能が通常扮装を伴って演技されるのに対して、落語においては扮装を排し、素のままで芸を見せるためである。すなわち落語では、噺家は登場人物や話の流れに相応しい身なりや格好をモノ(衣装・小道具・大道具・書割・照明・効果音)で表現することはなく、主として言葉と仕草によって演出効果をねらう。そのために、落語の表現要素は (1) 噺家の芸に結びつく基本的な要素(言葉、仕草)と (2) 1 を助けるためにその場に応じて何にでも変化できるようなニュートラルな最低限のモノ(小道具、衣装)とに区分することができるのである。これは、素の芸であることを前提とする落語の大きな特徴です。
談志師匠なんかは典型的な江戸落語ですね。喬太郎もそうですが、素であの表現力ですから、空道なんかやらせたらどんな技が出るか楽しみです。自分もイメージトレーニングとして取り入れようかな落語。もっと距離のとり方を勉強します。